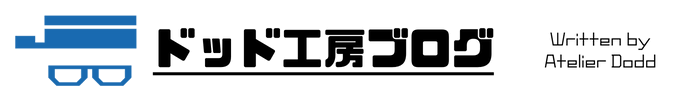ゲーム制作の流れ【個人ゲーム開発の場合を詳しく解説】


ゲーム制作を始めたいです。
でも、個人ゲーム開発って、どんな感じでやれば良いですか?
個人ゲーム制作の流れを教えてほしいです。
こんなご要望にお応えします。
この記事の内容
- 個人でゲーム制作する場合の流れを詳しく解説
- 各工程に必要なノウハウもご紹介
- 個人ゲーム開発とチーム開発現場のゲーム制作の流れの違いも解説
ゲームを制作するなら、どんな流れでゲームを作れば良いのかを知っておくだけで得します。
なぜなら、ゲームを完成させるためにやるべきことが明確になるからです。
つまり、ゲーム制作の流れを知っておけば、効率的に開発を進められるようになります。
ちなみに個人が行うゲーム制作の流れは、プロのゲーム開発現場の流れとは実は異なります。
大きな違いとして、企画書の作成やプレゼンテーションが必ずしも必要ではありません。
そこで今回は、個人ゲーム開発者向けのゲーム制作の流れを解説します。

各工程に必要なノウハウも紹介するので、参考にしてください。
この記事を読めば、あなたは個人ゲーム制作の流れを知り、役立つノウハウも手に入ります。
それではご覧ください!
ゲーム制作の流れ(個人ゲーム開発の場合)

さて、個人ゲーム開発におけるゲーム制作の流れは下記のとおりです。
- ゲーム制作に必要な開発環境を準備する
- ゲームのアイデアを考える
- ゲームに使う素材を用意する
- ゲームを組み立てる
- テストプレイしてデバッグする
- README.txt(説明書)を書く
- ローカライズ(多言語対応)をする
- ゲームをリリースする
- フィードバックを基に改善していく
各ステップについて、詳しく解説していきます。
ステップ①:ゲーム制作に必要な開発環境を準備する
まずは、ゲーム制作を始めるのに必要な開発環境を準備しましょう。
ゲームの開発環境として、以下のものが必要です。
- ゲーム開発用のPC
- ゲーム制作ツール(ゲームエンジン)
ゲーム開発用のPC
ゲーム制作をするには、原則としてPC(パソコン)が必要です。
それも、低性能ではない安定して動くPCでないといけません。
PCの性能が低いと、円滑にゲーム開発を進められないためです。
また、古いPCだと最新のゲーム制作ツールが動作しない場合もあります。
なので、あなたはゲーム開発に適したPCを必ず準備しましょう。
ちなみに、プライベート用のPCとは別個で用意するのをおすすめします。

制作するゲームデータ内に、あなたやご家族の個人情報が混入してしまうリスクを減らすためです。
ゲーム開発用にパソコンを選ぶ際は、以下の記事を参考にご覧ください。
»ゲーム開発におすすめのPCを厳選【必要なスペックと選び方も解説】
ゲーム制作ツール(ゲームエンジン)
ゲーム制作をするなら、ゲーム制作ツール(ゲームエンジン)を使うのがおすすめです。
ゲーム制作ツールを使うことで、リッチな見た目の本格的なゲームを作りやすくなります。
一応、ゼロからプログラミングしたり、ライブラリを活用する方法もあります。
しかし、率直に言って、美しい見た目の本格的なゲームを作るのは難しいです。
なので、基本的にはゲーム制作ツールを使ったゲーム開発にチャレンジすると良いでしょう。
以下の記事で、おすすめのゲーム制作ツールを紹介しています。
»ガチでおすすめのゲーム制作ツールは5つ!初心者向けに選び方も解説

ちなみに個人ゲーム開発では、UnityかRPGツクールMZ、またはBakinの3つが特におすすめ。
ステップ②:ゲームのアイデアを考える

率直に言って、個人ゲーム開発においては、アイデアを考える工程が最も重要です。
アイデアがよく定まっていない状態では、ゲームを作り始めても完成させるのが困難になります。

たとえ完成できたとしても、アイデアが悪いと駄作になりかねません。
また、身の丈に合ったアイデアを採用しないと、ゲーム開発の難易度が上がって完成が困難になることも。
オンラインゲームや美しい3DCGの大作ゲームなど、個人では実現が容易ではないアイデアも結構あります。
したがって、最初にある程度アイデアを考え、実現可能な内容で絞っておく必要があります。
さて、具体的に考えないといけない要素は下記のとおりです。
- ゲームのジャンル
- ゲーム性(ゲームシステム)
- 設定(舞台や世界観、主人公の置かれる状況など)
- ストーリー(シナリオ)
- キャラクター
- ゲームの雰囲気
それぞれ、どのようにアイデアを考えれば良いかを解説していきます。
ゲームのジャンルを決める
まず、どんなジャンルのゲームを作るかを決めましょう。
ジャンルごとで難易度が異なるので、まずは今のあなたに作れそうなジャンルで作るのがおすすめ。
ちなみに、各ジャンルの難易度の目安は下記のとおりです。
| ゲームジャンル | 制作の難易度(2Dの場合) | 制作の難易度(3Dの場合) |
|---|---|---|
| アクションゲーム(ACT) | 低~ | 高~ |
| ロールプレイングゲーム(RPG) | 中~ | |
| シューティングゲーム(STG) | 中~ | |
| アドベンチャーゲーム(ADV) | 低~ | 低~ |
| シミュレーションゲーム(SLG) | 高~ | 高~ |
| パズルゲーム(PZL) | 低~ | 中~ |

初めてゲームを作るのであれば、ADVかPZLが比較的作りやすくておすすめです。
ゲームジャンル別の制作難易度や人気度については、以下の記事で詳しく解説しています。
参考にご覧ください。
»ジャンル別ゲーム制作の難易度と人気度【初心者におすすめのジャンルも解説】
ゲーム性(ゲームシステム)を考える
ジャンルが決まったら、次はどんなゲーム性(ゲームシステム)で作るかを考えます。
なお、ここでお伝えするゲーム性(ゲームシステム)は、ゲームのルールや達成感(やりがい)を感じさせる要素のことです。
多くのゲームは基本的に、同じことの繰り返しで成り立っています。
あなたが作ったゲームのルールのもとで、プレイヤーに同じようなことを繰り返させるのです。
行動を繰り返させた際に、プレイヤーに「学習経験」を得てもらうようにするのがコツです。
そして、繰り返しのプレイを経て成功した際、「達成感」を感じてもらえるようにします。
目標を与える→行動させる→失敗を経験させる→反省(学習)させる→行動させる→目標達成時に報酬を与える
こんな感じです。

例えば、「敵から逃げるゲームシステム」のゲームを作る場合は、下記のとおり。
ゴールを提示する→敵から逃げさせる→捕まってしまう→捕まらないように工夫させる→敵から逃げさせる→逃げ切ることに成功(次のステージに進めたり、リザルトを表示したりする)
こんな感じで遊べるように設計するわけです。
プレイヤーに何を目標とさせ、どのように工夫させて行動させるか。
これを考えていくことが、私のお伝えするゲーム性(ゲームシステム)設計の基本です。
駆け引きに緊張感を持たせると、さらにゲームが面白くなる
桜井政博氏によると、ゲーム性という言葉について、下記のように定義されています。
ゲーム性という言葉を私なりに意訳すれば、「かけひき」。言い換えて、「リスクとリターン」と呼ぶことにしようと思います。
参照:「ゲームの面白さを生み、より高めるための法則とは?──『カービィ』『スマブラ』の生みの親・桜井政博氏による研究の集大成となる講演をWeb上に再現【若ゲのいたり・特別編】」電ファミニコゲーマー(最終閲覧:2025/4/29)
駆け引きに緊張感が生まれるようにすると、ゲームはいっそう面白くなります。
もし、クリア難易度を低く設定しすぎると、余裕すぎてゲームプレイが単なる作業になってしまいます。
緊張感がなくて作業感の強いゲームは、率直に言って面白いゲームとは言えません。
なので、面白くするために、駆け引きに緊張感があるゲーム性で設計しましょう。
刺激的でドキドキするような「エキサイティングなゲーム」を目指すのです。

わかりやすく言うと、「ギリギリでクリアできる感じに設計する」ということです。
時間制限やアイテム縛りをかけたり、HPやMPを少なくしたり、敵を強くしたり速くしたりと、手段はさまざま。
そして、ギリギリでクリアすればするほど、得られる報酬が多くなるように設計すると効果的。
達成した時の満足感が大きくなり、より難しい難易度でゲームを遊ぶ動機づけに繋がります。
設定(舞台や世界観、主人公の置かれる状況など)を考える
ここで挙げる「設定」とは、ゲームの舞台や世界観、主人公の置かれる状況などのことです。
ゲームの設定をしっかり定めておくと、ストーリー制作にも取り組みやすくなります。
例えば、設定の例としては下記のとおり。
| 舞台 | 日本/外国/海/宇宙/異世界など |
|---|---|
| 時代背景 | 現在/過去/未来など |
| 世界観 | 剣と魔法が使える/サイバーパンク/ディストピアなど |
| 主人公の置かれる状況 | 世界を救わないといけない/恋人を敵から助けないといけない/敵のアジトから逃げないといけないなど |

ただし、設定はゲーム性と合致する内容で考えるのが重要です。
ゲーム性と設定が合わない場合、その違和感でプレイヤーがゲームに没入しづらくなります。
なので、ゲーム性と整合性のとれた設定を考えましょう。
ストーリー(シナリオ)を考える
ゲームのストーリー(シナリオ)も、ゲームシステムにマッチする内容で考える必要があります。
ゲームという媒体で表現しにくいストーリーを選んでしまうと、制作が難航して苦労するからです。
また、たとえ完成できたとしても、微妙な出来になってしまう可能性が高いといえます。
ストーリーとシステムのミスマッチにより、没入感が損なわれてしまうためです。
例えば、「美少女との恋愛系のストーリーのシューティングゲーム」を想像してみてください。
これを違和感なく成立させて、かつ面白い内容で作れるでしょうか?
率直に言って、相当難しいと思われます。

例外として、どんなストーリーでも対応できるのは、ノベルゲームくらいでしょう。
なので、基本的にゲームのストーリーを制作する際は、ゲーム性との整合性を意識して取り組みましょう。
シナリオ制作の知識の有無で、完成度に差が出る
ちなみに、シナリオ制作の知識を持っているか持っていないかで、完成度に結構な差が出ます。
より良いゲームシナリオを作りたいのなら、勉強しておいて損はしません。

シナリオ制作の知識は、本を読んで学ぶのが良いですよ。
本は体系的に情報がまとまっているので、効率よく学習できるからです。
以下の記事で、物語づくりの勉強になる書籍を紹介しています。
»【厳選】物語の創作におすすめの本6冊【作り方の参考書】
キャラクターを作る
キャラクターも、ゲームの設定やゲーム性にしっかりマッチするように作る必要があります。
それを無視してキャラクターを作ってしまうと、違和感や矛盾が生じてしまいます。
例えば、「ロボットに乗って敵と戦うゲーム」を考えてみましょう。
このゲームで、もし「機械の操作が苦手な人物」をプレイアブルキャラクターとして登場させたらどうなるでしょうか?
プレイヤーの腕前が良ければ、そんなキャラクターでも簡単に敵を倒してしまいます。
すると、「機械の操作が苦手なはずの人物が、ロボットを自在に操って戦っている」という、設定との矛盾が発生してしまいます。

これがもし、機械の操作が得意なキャラクターであれば、矛盾は生じず、逆に説得力が生まれます。
したがって、キャラクターはゲームの設定やゲーム性に合った能力や性格を持たせることが重要です。
プレイヤーが共感できる主人公にしよう
ちなみに、主人公はプレイヤーにとって共感しやすいキャラクターにしましょう。
共感できる主人公にすることで、プレイヤーの没入感が高まるためです。
つまり、ストーリーに入り込みやすくなり、よりいっそうゲームを楽しませることができます。

逆に共感しづらいキャラクターにしてしまうと、プレイヤーは操作するのが嫌になってしまいます。
なので、ゲームにおける主人公は、人々が共感しやすいキャラクターにすることが重要です。
ゲーム全体の雰囲気を決める
制作するゲーム全体の雰囲気を決めましょう。
雰囲気づくりは軽視されがちですが、私の経験に基づくと実は結構重要です。
雰囲気は、用意する画像や音声などの素材にも大きく影響します。
また、ゲーム全体の雰囲気に統一感のない作品は、没入感を損なってしまいます。
なので、どんな雰囲気のゲームにするかは、必ず決めておきましょう。

ちなみに、ゲームの雰囲気の例としては下記のとおりです。
- 明るい または 暗い
- シリアス または ギャグやコメディ
- オシャレ または B級感
- 大人向け または 子供向け など
同じ題材でも雰囲気を変えるだけで、まるで別のゲームに感じられるほど、印象に違いが生まれます。
ステップ③:ゲームに使う素材を用意する

ゲーム制作をする場合、ゲームに使う素材(画像や音声など)を用意する必要があります。
素材を用意する手段は下記のとおり。
- 自分で素材を作成する
- フリー素材を活用する
- 素材の作成を依頼する
順番に解説します。
自分で素材を作成する
まず、ゲームに使う素材は、下記のとおり専用のソフトやツールを用いて作成します。
| 2DCG、イラストの作成 | ペイントソフト(クリスタなど)、画像編集ソフト(Photoshopなど)、ペンタブ |
|---|---|
| ドット絵の作成 | ドット絵エディタ(EDGE、Asepriteなど) |
| 3DCGの作成 | 3Dモデリングソフト(Blender、Mayaなど) |
| 効果音の加工や編集 | 音声編集ソフト(Audacity、SoundEngineなど) |
| 音楽の作曲 | DAWソフト(FL Studio、Cubaseなど) |
| ムービーの編集 | 動画編集ソフト(DaVinci Resolve、AviUtlなど) |

素材を作るためのツールについて、以下の記事で紹介しています。
実際に私も使用しているソフトなので、参考にどうぞ。
»私が創作活動に使っている実用的なツール【おすすめソフト】
素材の自作は大変だけどオリジナリティを出せる
率直に言って、自分で素材を作成するのは大変です。
作成の技術があるからといって、簡単に作れるわけではありません。

実際、私自身も素材を作成できますが、いつも必死に取り組んでいます。
それでも、なぜ多くの個人ゲーム制作者が、あえて自作にこだわるのか?
それは、ゲームに自分らしさを出せるからです。
単なる自己満足の面もありますが、実はオリジナリティはダウンロード数や売上に影響を与えます。
フリーゲームやインディーゲームを遊ぶユーザーは、基本的にその作家の個性的な表現を楽しみにしています。
逆に、フリー素材や有料アセットなど、既存の借り物素材ばかりを使っていると、魅力的に感じにくいです。
そのため、個人ゲーム制作においては、素材を自作して作者の色を出すのが大事なのです。
フリー素材を活用する
ゲームに必要な素材のうち、どうしても自分で作れないものは、フリー素材を活用するのも手段の一つです。
すぐにダウンロードして利用できるので、時間をとられず効率的にゲーム制作することもできます。

ちなみに、私の各種おすすめの素材サイトは下記のとおり。
| 素材サイト | 左記のサイトの特徴 |
|---|---|
| REFMAP~研究部~ | ゲーム用の高品質な無料ドット絵素材を入手可能 |
| BEIZ images | 無料テクスチャ素材を豊富なラインナップから選べる |
| 効果音ラボ | 高品質な効果音のフリー素材がたくさん手に入る |
| DOVA-SYNDROME | アマチュアだけでなくプロによるBGM素材も無料ダウンロード可能 |
| Unity Asset Store | Unity向けの素材が手に入る。無料素材もある |
ちなみに私も、まだ少しではありますが、フリー素材を公開しています。
»ドッド工房のフリー素材(ゲーム・アプリ・動画用)
フリー素材を利用する際は、利用規約(ライセンス)をよく確認しましょう。
中には商用利用などが禁止されている素材もあるので要注意です。
使うフリー素材はよく選び、使い過ぎにも注意が必要
フリー素材を活用すれば、簡単かつ効率的にゲーム開発できます。
なので、個人ゲーム開発においては、フリー素材はとても有難い存在です。
しかし、使用素材が他の作品と被りやすいというデメリットもあります。
つまり、あなたのゲームのオリジナリティが損なわれる可能性があります。
場合によっては、ユーザーからの印象を悪くしてしまうリスクも捨てきれません。

率直に言って、低クオリティなゲーム作品にも、フリー素材は頻繁に利用されています。
もし、ハイクオリティなゲームなのに同じフリー素材を使用していると、それだけで印象を悪くしてしまうことも。
また、特に有料ゲームを制作する場合は、フリー素材の使い過ぎには注意が必要です。
フリー素材ばかりのゲームだと、せっかく購入してくれたユーザーをがっかりさせてしまいます。
したがって、使うフリー素材はよく選び、使いすぎにも注意しましょう。
素材の作成を依頼する
「自分で素材を作るのは難しい、だけど独自性のあるゲームを作りたい!」
そんな場合は、素材の作成を依頼しましょう。
プロやセミプロに依頼すれば、ハイクオリティなゲーム素材を簡単に入手できます。
あなたの要望に沿って作ってくれる方も多く、あなたのゲームにマッチした素材を手に入れられます。

実際、私は作曲スキルは専門外なので、他のクリエイターにゲーム用BGMの制作を依頼しています。
また、ムービー編集のスキルも自負できるほどではないので、動画編集者として実績のある方にお願いしています。
他人に依頼する以上は、それなりの報酬を支払う必要があります。
しかし、本来自分がすべきだった作業の苦労を肩代わりしてくれるわけです。
ゲームのクオリティを高めるためなら安いものといえます。
場合によっては、可愛いアニメ系の女の子のイラストを1,500円から引き受けてくれる方もいます。
したがって、実は素材の作成依頼は、あなたが思っている以上に手軽なのです。
以下の記事で、ゲームに使う素材を依頼する方法を解説しています。
初めての依頼は不安が多いかと思いますので、参考にご覧ください。
»ゲーム制作の作業や素材作成を依頼する方法【手軽・格安で委託も!】
ステップ④:ゲームを組み立てる

アイデアも考えて、素材を準備できたら、いよいよあなたのゲームを組み立てていきます。
下記の流れでゲームを組み立てていきましょう。
- 素材をゲームフォルダに入れる
- マップを作る
- キャラクターを配置する
- セリフを入れていく
- ゲーム演出を作る
- ゲームシステムを作る
- ゲームUIを作り込む
順番に解説していきます。
①:素材をゲームフォルダに入れる
まず、ゲームに必要な素材を、ゲームのプロジェクトフォルダに入れます。
原則としてゲームは、このフォルダ内の素材を読み込んで使用するという仕組みです。

素材をフォルダに入れる際は、素材の種類ごとにフォルダを分けて整理します。
基本的に画像や音声など、異なる種類のファイルを同じフォルダに混ぜて格納することはしません。
フォルダ分けの方法は、ゲーム制作ツール(ゲームエンジン)によって仕様が異なります。
なので、あなたが使うゲーム制作ツールのマニュアルを参照しながら、素材を格納していきましょう。
半角英数字で分かりやすいファイル名で整理しよう
ちなみに、ゲーム内で使用するファイル名は、基本的に半角英数字を使用しましょう。
ゲーム制作ツールにも依りますが、漢字や記号などを用いるとエラーが発生する場合もあるためです。

また、ファイル名は誰でも分かりやすいものにしましょう。
自分自身が管理しやすくなるほか、ローカライズ(多言語対応)する際、翻訳者が理解しやすくなります。
②:マップを作る
次に、プレイヤーが操作できる「ゲームのマップ(ステージ)」を作成していきます。
マップを作る際は、単に見た目を作り上げるだけではありません。
プレイヤーが移動できる範囲と移動できない範囲を、設定する必要があります。
例えば、3Dゲームエンジン(UnityやUnreal Engineなど)を使用する場合、壁やオブジェクトにコリジョン(当たり判定)を設定します。
一つ一つのオブジェクトに対して衝突判定を設定しないといけないので、それなりに手間のかかる作業です。
一方、2Dゲームエンジン(RPGツクールMZやWOLF RPGエディターなど)を使う場合は、マス単位(タイル単位)で当たり判定を設定できます。
そのため、3Dゲーム開発に比べて比較的シンプルにマップ作成できます。

マップの作り込みはゲームの評価に割と影響します。
人々に「遊びたい!」と思わせるような、魅力的なマップを心がけて作りましょう。
ゲームのマップを作るコツ
私のこれまでの経験をもとに、ゲームのマップを作るコツをお伝えします。
ゲームのマップを作る際は、下記のことを意識して作りましょう。
- 見た目の美しさやリアリティよりも、ゲーム性を最大限に活かせる楽しいマップを心がけよう
- プレイヤーにとって移動できる場所が分かりやすいマップを作ろう
- 次にどこへ行くべきか、どこを調べるべきかが、色や形状で視覚的に伝わるマップを作ろう
- 移動操作で突っかかりやすそうな箇所は極力無くそう
- 見た目が単調にならないよう、壁や床に凹凸や模様などの変化をつけよう
- 理由や目的がないまま、むやみにマップを広くするのはやめよう
- キャラクターの部屋などは、その人物の暮らしぶりや性格が分かるように作り込もう
ゲームのマップを作る際は、プレイヤーがストレスなく快適に遊べるように設計することを第一に考えましょう。

ビジュアルやディティールの表現は、遊びやすさをしっかり維持したうえで作り込むべきです。
③:キャラクターを配置する
マップを作成した後は、マップ上にキャラクターを配置していきましょう。
キャラクターは、ゲームの世界観を深めたり、プレイヤーに情報を伝えるうえで重要な役割を果たします。
例えば、RPGに登場する村人のような存在です。
話しかけると、さりげなく攻略のヒントをくれたり、ときにはユーモアでプレイヤーを和ませたりします。

そんなキャラクターがいると、あなたのゲームがよりいっそう魅力的になります。
また、単に機械的な説明文で案内するよりも、キャラクターのセリフを通してプレイヤーを誘導するほうが自然です。
そのほうがプレイヤーも楽しく感じられます。
したがって、あなたのゲームをより魅力的にするキャラクターを配置していきましょう。
④:セリフを入れていく
マップ上に配置したキャラクターや、イベントシーンにおける主人公などに、セリフをつけていきます。
ゲームに登場するキャラクターのセリフは、プレイヤーをゲームに没入させるのに重要な要素です。
日常会話のように、親しみやすくてテンポの良いセリフ作りを心がけましょう。
セリフが堅苦しかったり難しい言葉ばかりになるのはNG。
プレイヤーが内容に入り込めなくなったり、ゲームを途中でやめてしまう原因にもなります。
セリフを作る際のコツは、「日常で友達と話すときのような自然な言葉」を意識すること。

説明セリフや書き言葉はなるべく使わないようにすべきです。
また、三点リーダー(……)やダッシュ(——)を多用するのも避けましょう。
あまり使いすぎると、テンポが悪くなって読みづらくなります。
そして、セリフを表示する際は、必要以上にウェイトを入れるのはやめたほうが良いです。
プレイヤーがストレスを感じる原因になります。
⑤:ゲーム演出を作る
映画やアニメと同じように、ゲームにも演出が欠かせません。
演出を丁寧に作り込むことで、ゲームはよりいっそうドラマティックになります。
その結果、プレイヤーの印象に強く残り、魅力的で面白いゲーム体験を提供できます。
例えば、次のようなゲーム演出があります。
- 必殺技を放つ際、迫力を増すエフェクトやカメラワークを加える
- ゲームオーバーの際、画面を一瞬止めたりシェイクや点滅、効果音を加えてみる
- シリアスな展開に移るとき、BGMを突然止めることで緊張感を高める
- ラスボスを倒した後、エンドロールの背景に平和が訪れた世界の風景を映し出す
- ホラーゲームにおいて、プレイヤーが油断したタイミングでお化けを登場させる

こういった演出は、既存のアニメや映画、そしてゲームから学んでいきましょう。
まずは有名作や人気のゲームを参考にして、演出を取り入れていけばOK。
その上で、あなたなりにアレンジや工夫を加えて、魅力的な演出を作り上げていくのがオススメです。
⑥:ゲームシステムを作る
「ステップ②:ゲームのアイデアを考える」で思いついたゲームシステムを実際に形にしていきます。
具体的に制作する要素には、以下のようなものがあります。
- ゲームルール
- プレイヤーが達成すべき目標
- キャラクターの操作方法
- HPやスキル
- 敵の配置や行動パターン
- レベルや経験値
- アイテムや装備
- 謎解きやパズル要素
- ストーリーの分岐や選択肢 など
つまり、ゲームの仕組みを作り上げる工程です。

ゲームの基盤を形成する非常に重要な部分といえます。
⑦:ゲームUIを作り込む
ゲームUI(ユーザーインターフェース)は、ゲームの見た目や使い勝手に大きく影響します。
なので、直感的に理解できるデザインで、誰でも使いやすいUIを作ることが重要です。
例えば、一般的に下記のUIを作る必要があります。
- HPゲージ
- ミニマップ
- スコアやノルマ残数
- 制限時間
- ボタンやアイコン
- 戦闘画面
- アイテム画面
- メニュー画面
- タイトル画面 など
これらのUIを作る際のコツは、視線誘導を考慮しつつ表示位置や視認性を意識することです。

私の経験上、基本的にZ字型の視線誘導でUIを配置していくのが分かりやすくてオススメ。
つまり、画面の左上→右上→左下→右下の順にプレイヤーの視線を誘導させるのです。
そして、HPゲージや制限時間など、プレイヤーがゲームを遊ぶ上で重要な情報から順番に表示していきましょう。
美しさより使いやすさがUIデザインの基本
ちなみに、UIデザインで色や形などの美しさに凝るのは、使いやすさを確保したうえで取り組むべきことです。
たとえ見た目が美しくても、使い勝手が悪ければゲームUIとしては本末転倒といえます。
もし、色彩感覚やセンスに自信がない場合は、白や黒などの単色でシンプルな見た目で作るのを推奨します。

見た目はやや地味になるかもしれませんが、無理に装飾を加えるよりはダサくならず、失敗しにくいです。
ステップ⑤:テストプレイして、デバッグやバランス調整をする
ゲームがある程度形になったら、テストプレイを実施します。
テストプレイでは、ゲーム内にバグや不具合がないかを細かくチェックします。
また、客観的に見て分かりにくい箇所がないかも確認しましょう。
さらに、難易度が高すぎたり低すぎたりしないかといった、ゲームバランスの調整も重要です。

なお、これらの点を確認する際は、後で見返せるようにメモを残しておきましょう。
ゲームでは、1つのバグが他の複数の不具合を引き起こすこともあります。
記録を残しておくことで、バグの関連性を見つけやすくなり、デバッグもしやすくなります。
このように、テストプレイやデバッグ、そしてバランス調整を進めていきましょう。
リリース前に可能な限りバグや不具合を取り除き、完成度を高めていくのです。
ステップ⑥:README.txt(説明書)を書く
ゲームが完成したら、ゲームの説明書(Readme.txt)を作成しましょう。
Readmeには、ゲームの概要や操作方法に加えて、利用規約(ライセンス)、免責事項、著作者情報なども記載する必要があります。
これらの情報を明記しないと、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
なので、ゲームを公開する際には、Readmeの作成は必須です。

決して手を抜かず、丁寧に説明書を作成しましょう。
ちなみに、ゲームの説明書の書き方は、以下の記事で詳しく解説しています。
参考にご覧ください。
»ゲームのReadme(説明書)の書き方【テンプレートあり】
ステップ⑦:ローカライズ(多言語対応)をする
ローカライズとは、ゲームを多言語に対応させるために、外国語に翻訳する工程のことを指します。
海外のユーザーにもゲームを遊んでもらえるようにするため、実は重要な作業です。
ローカライズを行うことで、より多くの方にゲームを遊んでもらえるようになります。
日本は人口が比較的少ないので、海外市場に展開することでダウンロード数やプレイ数の増加が期待できます。

実際に私の公開中のゲームのうち、6作品はすでにローカライズ済みです。
中国、台湾、韓国など、海外のプレイヤーにも遊んでいただいています。
特に、自作ゲームを販売したい場合は、ローカライズは積極的に行うべきです。
対応言語を増やすことで、売上アップのチャンスにつながります。
以下の記事では、ゲームをローカライズする方法を解説しています。
外国の方にもゲームを遊んでもらいたい場合は、ぜひ実施しましょう。
»自作ゲームを翻訳する方法【ローカライズで海外進出を狙おう】
ステップ⑧:ゲームをリリースする
完成したゲームをいよいよリリースします。
ゲームにはさまざまな公開方法があります。

日本の個人ゲーム開発者の場合、以下のようなサイトで公開することが多いです。
| フリーゲーム投稿サイト | フリーゲーム夢現、PLiCy、unityroomなど |
|---|---|
| ゲームやアプリの配信プラットフォーム | Steam、Google Play、App Storeなど |
他にも、自作ゲームを販売する際は、以下の記事で紹介しているサイトも活用できます。
»自作ゲームをネットで販売する方法【個人ゲーム制作者向け】
ゲームをリリースする際は、広報活動も忘れずに
ちなみに、単にゲームを公開するだけでは不十分です。
ゲームの魅力を伝える工夫や、宣伝などの広報活動が必要です。
広報活動をせずにリリースしても、実はあまり多くの方には遊んでもらえません。
せっかく頑張って制作したゲームですし、広報にも力を入れて、より多くの方に遊んでもらいましょう。

個人ゲーム制作者向けの広報活動のやり方は、以下の記事で解説しています。
あなたもゲームをリリースする際、参考にどうぞ。
»自作ゲームのDL数を増やす方法【無料でできる宣伝と見せ方のコツ】
ステップ⑨:フィードバックを基に改善していく
ゲームをリリースした後も、実はまだゲーム制作は続きます。
結局のところゲームは、ユーザーと共に完成させていくものだからです。
ゲームをリリースすると、遊んでくれたユーザーからフィードバック(感想や評価)が寄せられます。
このフィードバックをもとに、ゲームの問題点を洗い出し、改善していく必要があるのです。
特に、個人でゲーム制作している場合、自分では気づきにくい問題点も意外と潜んでいます。
外部の視点であるユーザーのフィードバックによって、それらの課題が浮き彫りになります。
それらの課題を着実に解決していくことで、ゲームの完成度はさらに高まるのです。

ときには、厳しい意見や理不尽なクレームが送られてくることもあります。
しかし、個人ゲーム制作者が成長するうえで、フィードバックは欠かせないものです。
積極的にフィードバックを受け入れ、あなたのゲームをブラッシュアップしていきましょう。
個人ゲーム開発とチーム開発現場のゲーム制作の流れの違い

以上が、個人ゲーム制作の流れです。
ここからは、「個人ゲーム制作」と「ゲーム開発現場(ゲーム会社のプロジェクトなど)」における、ゲーム制作の流れの違いについて解説していきます。
冒頭でも触れたとおり、個人が行うゲーム制作の流れは、プロのゲーム開発現場の制作フローとは異なります。

中でも違う点として、下記の点が挙げられます。
- 個人ゲーム制作では、ゲームの企画書の作成は必ずしも必要ではない
- 個人ゲーム制作では、プレゼンテーションは必ずしも行う必要はない
- 個人ゲーム制作では、ゲームの仕様書の作成も必ずしも必要ではない
順番に解説していきます。
違い①:ゲームの企画書の作成は必ずしも必要ではない
ゲームの企画書とは、ゲームのアイデアや構想をまとめたものです。
実際のゲーム開発現場(ゲーム会社のプロジェクトなど)では、企画書を使って制作するゲームの情報をチームで共有します。

つまり、複数人でのゲーム開発において、企画書は重要な役割を果たすのです。
一方、個人でゲームを制作する場合は、基本的に企画書を作る必要はありません。
文字通り一人で制作するので、他人と情報を共有する場面がないためです。
ただし、例外も一応あります。
例えば、クライアント(依頼者)からゲーム制作を受注している場合です。
このような場合、相手と情報共有するために企画書が必要になることがあります。
とはいえ、このようなケースは基本的に、ゲーム制作の経験をある程度積んだ方が関わることです。

これからゲーム制作を始める方には、まだあまり関係のない事例かもしれません。
なので、個人でゲーム制作する場合は、必ずしも企画書を作る必要はありません。
もし作るとしても、自分用に構想をまとめたメモ程度で十分です。
違い②:プレゼンテーションは必ずしも行う必要はない
ゲームの企画を伝えるためのプレゼンテーションは、そのゲームの魅力を伝えるために重要な手段です。
特に、上司や共同で制作するチームメンバー、依頼主(クライアント)に対して、ゲーム内容を魅力的に紹介することが求められます。

実際のゲーム開発現場では、こういったプレゼンテーションがほぼ必須と言えます。
一方、個人ゲーム制作の場合、プレゼンテーションは基本的に不要です。
個人ゲーム開発者は、基本的に自分一人でゲームを企画し、自身の資金と労力で制作を進めることが多いです。
そのため、プレゼンテーションを行う必要がほとんどありません。
ただし、例外もあります。
例えば、依頼主がいる場合や、クラウドファンディングを利用してゲーム制作する場合などです。
このような場合、企画しているゲームの内容や魅力をプレゼンテーションで効果的に伝える必要があります。
とはいえ、こちらも企画書の場合と同様、ゲーム制作にある程度経験を持った開発者が行うことがほとんど。

なので、個人ゲーム制作でプレゼンテーションを行う機会は滅多にありません。
違い③:ゲームの仕様書の作成は必ずしも必要ではない
ゲームの仕様書とは、ゲームの内容や構成要素をまとめた文書のことです。
主にチーム間で情報を共有したり、開発に必要な作業を確認するために作成します。
実際のゲーム開発現場では、ゲームの仕様書は非常に重要です。
最終的に納期に間に合わせるためには、仕様をしっかりと定めておくことが欠かせません。
仕様書が曖昧だと、開発の進行に遅れが生じたり、工程管理がうまくできなくなる可能性もあります。
プログラマーやデザイナー、デバッガーなどの間で認識のズレが生じるからです。

ただし、ゲームの仕様書は、主にチーム開発やプロの現場で必要とされるものです。
個人でゲーム制作する場合、必ずしも仕様書を作成する必要はありません。
自分の頭の中で構想をしっかりと持っていれば、仕様書がなくてもゲーム開発を進めることは可能です。
とはいえ、個人開発でも大作や長編ゲームの制作、またはマルチプラットフォーム展開する場合は、仕様書を作成しておくと整理しやすくなります。
ただし、初心者の場合、仕様書を作ったとしても、その通りに作り上げるのが難しいこともあります。
技術力と理想とのギャップがあるため、仕様書を作ること自体が時間や労力の無駄になってしまうこともあるのです。
とはいえ、もし実際のゲーム開発に則って取り組みたいのであれば、練習として仕様書を作成してみるのも良い経験になります。

もし興味がある場合は、「ゲーム 仕様書」といったキーワードで検索してみましょう。
実際のゲーム会社が研修などで使用している仕様書を閲覧可能です。
まとめ:ゲーム制作の流れを知ったら早速ゲーム開発しよう!

今回は、個人ゲーム制作の流れと、個人ゲーム制作とプロの現場のゲーム開発の違いを解説しました。

ゲーム開発者によって多少は異なりますが、個人ゲーム制作の大まかな流れはこんな感じです。
これであなたも、個人ゲーム制作の流れと各工程のノウハウの一部を知ることができました。
さっそくあなたも、ゲーム制作にチャレンジしてみましょう!
実際にゲームを作ってみたいと思ったら、以下の記事をご覧ください。
ゲーム制作の始め方から学習方法、ゲームのリリース方法まで詳しく解説しています。
»ゲームの作り方:初心者向けに個人ゲーム制作の始め方とノウハウを解説